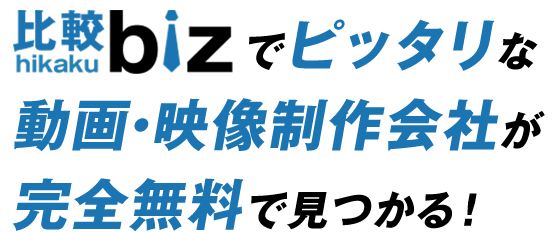動画制作はどこまで外注すべきか?制作分担とAI活用の最適解
本記事では、動画マーケティングのプロである株式会社AtoOne代表・松下 勇介さんへのインタビューを通じて、制作工程の分担ポイントやAI活用の最前線、そして内製を成功させるための考え方を掘り下げます。

株式会社AtoOne代表。動画マーケティング支援サービス「Mteam」を運営し、企画から制作・運用まで一貫して支援。企業ごとの目的に応じた柔軟な体制構築と成果につながる動画を提案する。
動画マーケティングの“分業と内製”
ーー今回の調査では内製比率が多く、一部内製も含めると約9割の企業が内製していると回答しています。内製で動画制作に取り組む企業が約9割はかなり多いと思うのですが、業界全体でどのような変化が起きているのでしょうか?
松下:まず、動画を制作・活用する企業がここ数年で一気に増えました。採用やブランディング、広告など、目的も多様化してきていて、動画を「継続的に作る前提」で体制を考える必要が出てきたんです。その中で、内製・一部外注・フル外注という3つのパターンが生まれてきた印象です。
ーー内製や外注の体制は、企業の規模によって傾向はありますか?
松下:自社で広告運用をしている企業では、PDCAを高速で回す必要があるため、撮影・編集を内製化するケースが多く見られます。
一方で、採用やSNS運用などでは企画力やキャスティングの専門性が求められるため、企画部分だけ外注する「一部外注」と、まるごと外部に任せる「完全外注」の企業も存在します。
ーー動画活用が広がった背景には、どんな要因があるのでしょうか?
松下:コロナで対面での採用や営業活動が難しくなったことが大きいですね。たとえば採用でいうと、動画を使った会社紹介や説明会のニーズが高まりました。
“おうち時間”の増加によってYouTubeなどの動画視聴が定着して、「動画を使った発信は効果的だ」と実感するようになったんですね。2020年から一気に動画広告の需要が盛り上がった印象です。

企画と制作体制の考え方
ーー企業に内製の選択肢が増えたとのことですが、実際の制作工程を分けて考えたとき、「ここはプロに任せた方がいい」「ここは社内でもできる」といった判断は、どこで分かれるのでしょうか?
松下:商品紹介のプロモーション動画であれば、「撮影・編集」は間違いなく外注をおすすめします。
理由はシンプルで、見せ方次第で成果が大きく変わるからです。綺麗に撮るのか、演出で魅せるのか、CGを使って世界観をつくるのか。どれもスキルが必要です。
ーーたしかに、演出次第で印象がまったく変わってきますもんね。
松下:そうなんです。逆に「企画」部分は内製がいいですね。社内の方が商品理解が深いぶん、的確なアイデアが出やすいこともあります。
もちろん構成作家やディレクターの力を借りることで、さらに視点が広がることもあるので、「企画を磨く目的」で外部の知恵を借りるのもありだと思います。
ーーtoB向け動画だと、内製の方が知見があってリアリティを出せる場面も多そうですね。
松下:「どこを自分たちで担い、どこをプロに任せるか」という判断軸を持つことが、今後ますます大切になってくると思います。
企画設計は“誰に届けるか”がカギ

ーーtoB向け動画にはやはり「堅くまじめに作るべき」といった考え方を持ってしまうのですが、作り方としてどう考えるべきでしょうか?
松下:確かに、そういった固定観念はまだ根強くあります。ただ最近は、SNSなどを通じて情報収集するBtoBの決裁者も増えていて、「少し柔らかめの表現の方が刺さる」というケースも出てきています。
ーー柔らかさとなると抽象的ですが、たとえばどんなコンテンツが有効ですか?
松下:BtoCで使われるようなストーリーテリングや、個人のキャラクターを押し出したコンテンツなどですね。
もともとtoC向けの手法だった企画が、toBの世界でも有効になってきている印象です。「toBだから堅く」「toCだから柔らかく」ではなく、“誰に届けるか”を明確にすることが、企画設計のカギになっています。
ーー企画において、届けたい相手の解像度を上げることが求められるわけですね。
松下:商品やサービスをよく理解しているのは、やっぱり自社の方なんですよ。だからこそ、伝えたいメッセージの骨子をしっかり固めるという意味では、企画を社内で詰めていくのも十分ありだと思います。
撮影や編集といった“映像のクオリティに直結する工程”は、やはりプロに任せた方が成果につながりやすいです。逆に企画は、目的と届けたい相手が明確になっていれば、社内で考えても十分通用する。そういった分担のバランスが、これからの動画制作では大事だと思います。
スピード重視の内製とコンサル支援

ーー動画制作では「スピード」と「クオリティ」の両立が理想ですが、現実には難しいと感じてしまいます。BtoB向けプロモーション動画の場合、この2つをどう両立すればいいのでしょうか?
松下:たしかに、多くの企業が悩むポイントですね。ただ最近は、「小さく始めて改善する」ことを前提に設計することで、スピードとクオリティのバランスを取るやり方が定着してきていると感じます。
ーー具体的にはどういった方法があるのでしょう?
松下:最初から「A/Bテスト前提」で企画しておくと、パターン違いを同時に検証できます。広告であれば、冒頭のメッセージやカットを差し替えるだけでも大きく印象が変わりますし、それだけで複数ターゲットに対応できます。
構成や編集の柔軟性をあらかじめ持たせておくことで、スピードを落とさずにPDCAを回すことができるんです。
ーー完璧な1本を目指したくなりますが……。
松下:完璧を目指すより、変えられる余地を設計しておくんですね。完成品を一発で当てにいくよりも、検証できる状態になっていれば、求める結果に対するチューニングがしやすくなりますよ。
「とにかく作りたい」ニーズにどう応える?
ーースピード重視で「とにかく早く出したい」「すぐ反応を見たい」という企業も多いと思います。スピード重視の企業であれば、やはり内製が向いているのでしょうか?
松下:はい、そういった場合は内製の方が適していることが多いです。たとえば、広告やLP用に毎週新しい動画を出す必要があるビジネスでは、外注ではやり取りの時間がボトルネックになってしまいます。
ーーたしかに、スピードが求められる現場では、外注だけで回すのは難しそうですね。
松下:DtoCのサービスなどでは、広告を量産してPDCAを高速で回す必要があるため、「やりたい」というより「やらざるを得ない」というケースが多い印象です。
ーー内製には専門知識も必要ですよね。スピード感とクオリティを両立するために、外部支援が必要な場面も多いのでは?
松下:動画制作って、企画・撮影・編集など関わる工程が多く、どこに工数やコストがかかるかが初めての方には見えづらいんです。
内製していくためには、1つずつの工程を理解した上で工数やクオリティのバランスを把握する必要があります。工程別の状況を把握した上で外部支援を受けると、よりブラッシュアップできて良いです。
ーーそういった“見えづらさ”をカバーできるのが、松下さんのようなマーケティングや動画制作を一気に支援できるプロなんですね。
松下:その通りです。僕たちは「まず作ってみたいけど何から始めたらいいか分からない」という状態に対して、外部が設計段階から伴走できるので、スピードを損なわずにクオリティも担保できる体制が整っていきます。

AIで変わる動画制作の“中身とスピード”
ーーAIや編集ツールなど、さまざまな技術が日々進化していますが、制作現場に影響はありますか?
松下:間違いなく動画制作のハードルを下げていますね。短尺の広告動画で、スライド素材を読み込ませるだけで自動的に動画化できるツールも多いですし。実際、AIツールを活用して広告動画を量産しながらビジネスを展開する企業も出てきています。
ーー具体的にどのような変化が起きているのでしょうか?
松下:変化で言うと、大きくは3つあります。
1つ目は、データの「見える化」です。たとえば広告動画のパフォーマンスをAIが自動で分析して、「どこを改善すべきか」を提示してくれるんです。これまで人が仮説を立てていた工程を、かなり高精度で代替できるようになってきました。
ーーなるほど、データ面の支援ですね。
松下:2つ目は、「制作工程の時短」です。AIで台本の素案を作ったり、画像生成AIでサムネイルを用意したり。短尺広告であれば、AIだけで制作が完結するケースもあります。特に海外ではすでに一般的になりつつあります。
3つ目は「AIエージェントとしての活用」です。弊社でもAIを、人の代わりにデータを分析・改善提案まで行う役割として使っています。「24時間働けるスタッフが増えた」ような感覚ですね。

それでも人の力が必要な場面
ーーAIがこれだけ進化しているといずれ丸投げできちゃうんじゃないかと素人目線で考えてしまうのですが、人間にしかできない部分もあるでしょうか?
松下:ありますね。AIで企画を出すと、どうしても平均点に寄りがちなんです。「感情を動かす」「印象に残る構成にする」といったクリエイティブな判断は、まだ人の力が不可欠です。カットの選び方や緩急の付け方など、映像表現のニュアンスは、AIにはまだ難しい部分が多いですね。
ーーSNSなどを見ていると、AIへの不安や反発も根強い印象です。実際の現場ではどうでしょうか?
松下:クリエイティブに活用しようとすればするほど、AIに対する抵抗感は強い印象があります。とくに現在のAIの技術では「似たような仕上がりになる」「人体や空間などの構造が正しく描かれていない」という直感的な不安があるんだと思います。
さらに著作権のグレーさもあって、「よくわからないから使いたくない」という声もありますね。
ーー便利であることに対して若干の罪悪感を感じる人もいますよね。
松下:そうですね。特に現場感を大事にする業種の方ほど、「これは仕事と言えるのか?」という感覚的な拒否感もあるように思います。
でも実際にAIのアウトプットを見せると、「便利だね」と評価が変わることも多いんです。まずは一部の作業だけAIに任せてみることで、成功体験が広がっていく。それが社内浸透の第一歩になると感じています。

動画マーケティングはどう進化するか?
ーーここから先、AIを含めて動画マーケティングはどのように変化していくとお考えですか?
松下:今後は「AIを積極活用する企業」と「人の力にこだわる企業」で、体制がはっきり分かれていくと思います。
たとえば、広告やSNS用の動画のようにPDCAサイクルが早く、データで改善が進む領域ではAIがますます主役になっていくでしょう。構成や編集もAIが担って、最短で成果を出す体制を構築する企業が増えていくはずです。
ーー人が担う領域も残り続けるのでしょうか?
松下:ストーリーテリングや表現力が求められる領域では、今後も人の役割はなくならないと思います。
テレビCM、ブランディング動画、採用向けのドキュメンタリーなど、「人の感情に訴える動画」は、AIよりも人の感性が強く求められる分野です。
実際は、「どちらかを選ぶ」のではなく、目的に応じて柔軟に組み合わせるのが一番効率的だと思います。たとえば広告ではAIを活用して数を出し、ブランド動画では人間の演出力に頼る——そういうハイブリッド型の制作体制が今後は主流になっていくのではないでしょうか。

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
見積もり依頼なら比較ビズ
翌日には平均8.3社から
見積もり提案が届きます
-
最大30社
比較可能 -
運営歴
21年目 -
マッチング実績
18万社超

動画編集・映像に関連する記事
-
2025年12月02日動画編集・映像美容室の集客に欠かせない動画活用方法8選|メリットや動画作成のコツを紹介
-
2025年12月02日動画編集・映像化粧品のプロモーション戦略には動画がおすすめ!面白いPR事例5選
-
2025年07月24日動画編集・映像動画制作はどこまで外注すべきか?制作分担とAI活用の最適解
-
2025年07月02日動画編集・映像展示会用の動画を制作する注意点4つとは?動画を制作会社へ依頼するメリット3つ
-
2025年06月16日動画編集・映像動画マーケティングの費用対効果はなぜ見えない?KPI設計と“数字だけじゃない” …
-
2025年05月13日動画編集・映像PR動画は制作会社に依頼できる?おすすめ制作会社6選や依頼手順を徹底解説